彼女が異種族だった場合。~教え子ヴァンパイアの甘トロ隷属調教~
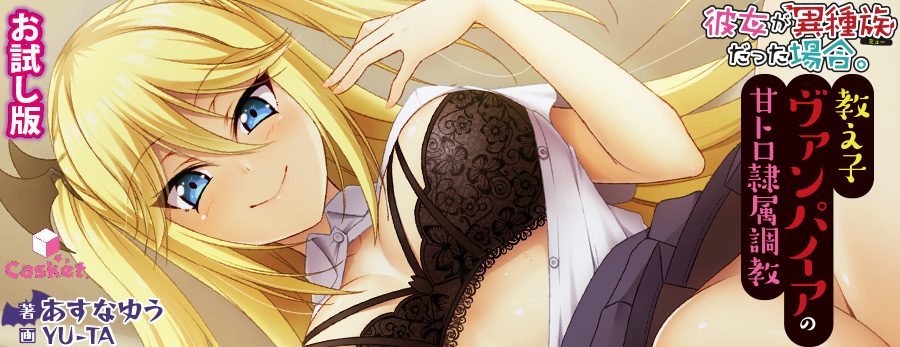
2018年9月1日
ぷちぱら文庫
著:あすなゆう
画:YU-TA
原作:Casket
放課後、夕方六時過ぎ。
桂樹はいつもどおり、教室でミラの相手をしていた。
太陽の光の苦手なヴァンパイアは明るい時間に出歩くことを嫌う。それはミラも同じで、彼女は日が暮れるまで教室で過ごしてから、家に帰ることが日課になっていた。
転校生で、まだ友達もいないミラ。その相手を桂樹がいつもしてやっていた。
ミラの手にはRHマイナスの血液ジュースのパックが握られていた。桂樹が打ち合わせで遅くなったお詫びにと、買ってきたものだ。
「悪かったって、言ってるだろ。そんなに拗ねるなよ、黒十字」
「拗ねてないし……今日はせんせが来てくれないのかな、って、ちょっと寂しくなっただけだもん」
ミラの瞳はかすかに潤み、切なそうな思いがそこから直に伝わってくる。
「せんせのことなんて、知らないッ」
ミラはぷい、とそっぽを向くと、血液ジュースをちゅうちゅうと啜り飲む。
彼女が血液を飲むたびに、さらけだされた真っ白な喉が艶めかしく動く。
美味しそうに血液ジュースを飲む黒十字ミラはまごうことなきヴァンパイアだ。
近年のヴァンパイアは人との混血も進んで、人間同様の食事でも栄養を得られるそうだが、元来は人間の血液のみを栄養にして生きる種族だ。
ミラの一族は純潔を守り通している古くからの名家で、彼女自身も人間の血液がなくては生きていけない。コンビニで血液ジュースが簡単に手に入る時代になったとはいえ、なかなか難儀な身体だと思う。
人間とヴァンパイアの共存にあたって、法律で原則、吸血行為を禁止している。もちろんミラも実際に人の生き血を吸ったことはないらしい。
桂樹がミラの放課後の時間つぶしにつきあいはじめて一ヶ月。
初めは転校生を気遣って、放課後を一緒に過ごしていた桂樹だったが、彼女の端正な美貌と年相応の愛らしい雰囲気に、次第に惹かれていった。
そうして、今、桂樹は彼女のことが本気で好きになっていた。
だが、教師と生徒。その立場を越えて、道ならぬ恋に踏みこむほど子供ではいられなくなっていた。
ふと気づくと、ミラがじっと桂樹のほうを見つめていた。
かすかに潤んだブルーの瞳に、赤らんだ頬。眼差しのあまりの熱っぽさに、そのまま引きこまれてしまいそうなほどだ。
「どうした、黒十字? 顔に何かついてるか?」
「ううん、なーんにも。ミラもせんせとお話できてうれしいなって、えへへっ♪」
「……そうか。そりゃよかった」
満面の笑みを浮かべるミラを見つめていると、本気になったまま戻れなくなってしまいそうで、慌てて視線を逸らす。
(俺が同じ学生の身分なら、失恋覚悟で告白することもできたのにな。さすがに今は、世間体ってものがあるしなあ……)
いつの間にか日はすっかり暮れ、夜の帳が降りつつあった。
ミラは桂樹の顔から視線を外さないまま、
「ねえ、せんせ?」
唐突に口を開く。
「結婚しないの?」
「け、結婚?」
いきなりミラに問われて、戸惑ってしまう桂樹。
「うん。せんせが考える理想のケッコン生活って、どんななのかなーって」
「結婚なあ。確かに親からはうるさく言われてるけど??」
結婚と問われて、ウェディングドレス姿のミラが急にイメージされて、桂樹は少し焦ってしまう。その妄想を打ち払おうとして、続いて出てきたのは裸エプロンのミラ。大きく盛りあがった爆乳のミラにエプロンはよく似合っていた。
「まあ、普通だよ。普通に専業主婦してもらって、俺が働いてかなあ。共働きだと、気持ちがラクかもだけど、ずっと家にいてほしいって気持ちも強いな」
「それ全然ロマンチックじゃなーい。愛し合ってるんなら、ずっと一緒にいるもんなんじゃないの。仕事のことばっかり……」
高校生のミラにはさすがに現実的すぎたのかもしれない。
「生きていくには仕事をしなきゃいけないんだから。それが社会のルールだしなあ」
「ルールかぁ……。じゃあ、次はミラがお話しする番ね」
いきなり桂樹の顔に自分の顔を近づけてくるミラ。吐息がかかるほどの距離で、彼女の瑞々しい唇に目を奪われてしまう。
「ミラの理想のケッコン生活は、せんせと暮らすこと」
「え!?」
いきなりそう言われて桂樹はドキリとしてしまう。
「ミラね、せんせのことが好きなの」
顔同士が触れるか触れないかの距離で、ヴァンパイアの少女は甘く囁きつづける。
「せんせの気持ち、ミラは知ってたよ。気づいちゃったの。だからミラは、せんせのほうから告白してくれるものだと思ってた。でもせんせは絶対にそうしない、いやできない……」
「ちょ、何を?」
ミラは両の眼で、戸惑う桂樹を見詰めつづける。
桂樹は本心を悟られまいと目を逸らそうとしたが、できなかった。彼女の魔力をこめられたような視線から目を離すことができない。
「ミラが聞きたいのはせんせの気持ち。せんせは……ミラのことをどう思ってるの?」
彼女に好意を持ってもらえるのは飛び上がりそうなほどうれしかったが、桂樹は教師でミラは生徒、その気持ちを受け入れることができないのも事実だ。
桂樹は嘘をつく罪悪感に押しつぶされそうになりながらも、なんとか口を開く。
「ごめんな黒十字。俺はお前とは……」
「つきあえない。だけどミラのことはすき、立場的にそれを言えない、ってこと?」
「なっ!?」
桂樹の本音を見抜いたかのように、ミラは強く指摘する。
「そんな大人の事情を聞きたいんじゃない。せんせの本当を聞きたいの」
ミラは桂樹の股の間に太腿を入れ、身体を密着させてくる。大振りの乳塊がぎゅっと押しつけられ、極上の弾力に何も考えられなくなってしまう。
「あっ……やめてくれ、ミラ……」
「せんせの心臓、すっごくドキドキしてる。ミラに告白されたから? それともミラに抱きつかれてるから?」
ぐいぐいと巨乳を押しつけられながら、ミラの甘い言葉が耳孔に流しこまれていく。
「せんせ、焦っちゃって……かーわいー♪」
「く、黒十字ッ! 先生をからかうのも大概にしろ!」
立場上、怒って見せながらも、可愛いと嘲られて、性的な悦びを感じてしまう。
「ミラはせんせの本心を聞きたいな? ねえ、教えてよせんせ??」
教え子のしなやかな手指が頬を撫で、そのまま首筋へと下りていく。背すじを走るぞくぞくとした後ろ暗い悦びに飲まれそうになってしまう。
「俺はお前とは、黒十字ミラとはつきあえな??いや、つきあわないっ! それが本心だ、他には何もないからな!」
桂樹は最後に残った理性を振り絞って、ミラを強引に引き剥がした。
「ううっ……」
ミラは怯えたように、少し後ろに下がる。彼女の前で本気で怒ったのは初めてだ。
「せんせ……ごめん、なさい」
「……いや、俺のほうこそすまない。つい感情的になってしまった」
俯きかげんに謝るミラを見て、桂樹は心が痛む。
(……いや、これで良いんだ。ミラにとっても、そして俺にとっても)
桂樹は無理やり自分を納得させる。
「……わかった。ミラ、せんせのこと諦める。やっぱり駄目だよね、せんせと恋人になるだなんて」
急にしおらしくなるミラ。どうやら彼女もわかってくれたらしい。
「今は、な。だけどもし、黒十字が大人になって、そのときにまだ俺のことが好きなら……もう一度。その言葉を聞かせてくれ」
「せんせ……くすっ、キザな台詞」
「もう、この話はこれで終わりな」
桂樹はその場が収まったことに、ホッと胸を撫で下ろす。
「じゃあせんせ、最後にひとつだけ……お願いしてもいい?」
「お願い?」
ミラは瞳をかすかに潤ませながら、じっと桂樹のほうを見てくる。
「せんせの顔……もう一度近くで見たいの。だめ?」
イヤと言える雰囲気ではなかった。
「う……わ、わかった。見るだけだからな」
「くすっ。ありがと、せんせ♪」
ゆっくりと顔を近づけてくるミラ。桂樹も内心ではミラのことを完全にふっ切ったわけではなかったから、キスの距離まで迫ってくるミラを直視することができなかった。
(これで最後か……)
桂樹は目を瞑って、ミラの甘い香りや吐息を感じる。今後はミラの身体には触れないし、触れさせない。恋人のように寄りそうのも最後だ。
「……ねえ、知ってるせんせ?」
甘くて、それでいて奈落の底に引きずりこまれ、そのまま戻ってこれなくなりそうなほど淫靡な声でミラが囁きかける。
学生とは思えないほどのエロティックな囁きに桂樹は息を飲んでしまう。
「ヴァンパイアに血を吸われた人間はね、ヴァンパイアの言うことには逆らえなくなるの。はふ、ふぅ~ッ」
「え……」
首筋にミラの湿った吐息がまとわりついたかと思うと、唇が触れる。
見るだけじゃなかったのか??そう、言い返そうとした刹那、首に突きさすような痛みが走る。
「かぷっ……んんっ」
「が、あ……!?」

直後、背すじを貫く快楽の奔流に、桂樹は声を上げることしかできなかった。
何をされたか、理解さえ追いつかない。
「な、なんだ、これっ……うううぅぅッ……ぅぅ……」
射精の快美感を何回も重ね合わせたかのような、濃密で激しい喜悦が全身を包みこんでいく。桂樹は立っていることさえできず、がっくりと片膝をついてしまう。
「はぁっ、これがせんせの血??初めて吸う、生の血? んく、んく、んくくッ、はぁああぁぁぁッ、こんなに美味しいだなんて、ミラ、吸血するだけでイっちゃいそう……せんせの熱い血を吸っちゃったら、もう血液ジュースなんて絶対、飲めない???」
「あくぅッ……黒、十字。まさか……」
桂樹はぼんやりとした頭で、ミラを見る。彼女の唇は赤のルージュを引いたかのように真っ赤な血液に彩られていた。
ミラの唇を見て初めて、桂樹は吸血されたことを理解する。
「せんせ、今どんな感じ? 頭ボーッとする? 身体が熱い?」
ミラはおずおずと桂樹の様子を窺う。
「今、何したんだ、お前……」
桂樹はミラのことを批難がましい目で見てしまう。
吸血は、法で禁じられた行為??犯罪だ。
目の前で一線を越えてしまった生徒に対して、憤るなというほうが無理だ。
「だってせんせは、全然自分に素直になってくれないんだもん。ミラ、どうしてもせんせと恋人になりたい。だから無理矢理、せんせを吸血して、素直になってもらおうと思ったの。大人の決めたルールとか関係ないもん……」
ミラの目は本気だった。
愛らしい生徒のそれではなく、美しい捕食者の目。幾星霜、人の血を吸いつづけてきたヴァンパイアの目だ。
「……もう少しせんせの血ぃ、飲んでみたいな。ね、良いでしょ?」
「い、いい加減にしろ黒十字、これ以上は……!」
ふいにミラの瞳が紅く染まっていることに気づく。
普段の碧眼ではなく、真っ赤な血で染めあげた真紅の双眸が桂樹を射抜く。
「こっち来て。ミラに血ぃ、飲ませて?」
桂樹の身体に自由意志はなかった。
(あ、あれ? どうして俺は、自分からミラに近づいているんだ?)
ミラから離れるべきだという自らの意思とは裏腹に、桂樹はミラの足元にひざまずいて、首筋を彼女のほうに晒していた。
「くすっ、優しいねせんせは。それじゃあ、いただきまーす♪」
ミラに吸血される快楽にもう一度襲われてしまえば、世間体も何もかも、投げ捨ててしまいそうで恐ろしかった。
(やめてくれ、またあの快感が襲ってきたら……!)
桂樹はなんとか抗おうとするものの、身体の自由が利くことはなく、ミラの二本の牙に再び吸血される。
首筋にめりこんでくる、ミラの鋭い歯の感触。
ずぷ、ずぷぷと。体内にミラが潜りこんでくるのがはっきりとわかる。唇のぬめりと、熱い吐息が刺さった牙の周りを覆いつくし、ヴァンパイアの少女に捕食されたことがはっきりと理解された。
「ぁ……ぁぁ……」
恐怖と緊張で、声を出すこともできない。教え子だった少女が別の何かに変質しているのをはっきりと見せつけられてしまう。
ほどなく血液が体外へと吸いあげられ、同時に蕩けるような愉悦が脳を甘く締めつけてくる。
「かぷ、んっ……ちゅぅ、んちゅっ、んっ。れろ、ちゅう」
「あひっ、血が吸われて……ぁああぁぁ……」
血が勢いよく抜けると共に、凄まじい量の快感がそれに置き換えられていった。
ペニスは一瞬で最大限勃起し、血のひと吸いごとにびくびくと先走り液を吐きだし、下着はぐっしょりと濡れていた。
「れる、ちゅ、んっ……はぁっ、最高、もっと吸うね♪ せんせ、ミラにちゅーちゅーされるの、気持ちいい?」
「や、やめて、くれえ……あひ、ぁひぃいいぃ……あぐ、あぐぐぅ……」
イキたい、精液を出したい、というどす黒い欲望が桂樹の頭を埋め尽くし、他の理性的な思考を掻き消してしまう。
ヴァンパイアの『力』のせいで手足を動かすこともままならない。桂樹はブツへの刺激を求めて腰を上下に動かす。ズボンの裏側が勃起の先にわずかに擦れるだけで、苦しみは増す。生徒の前だというのに、その浅ましい行為をやめることができない。
「やめてくれ? 違うでしょ、せんせ。心の奥底ではそんなこと考えてないよね?」
ミラは真紅に染まった瞳で、桂樹をじっと見る。
「せんせはぁ、ミラにどうされたいの?」
その紅い目に捉えられると、桂樹は桂樹でなくなってしまう。
自らの意思に反し、口が動く。
心の奥底にしまっておくべき、どろどろした薄汚い欲望が喉奥からせりあがってくる。
「俺はもっと、吸われたい……血も、精液もっ……全部、黒十字に、可愛いミラに、吸われたいッ……」
一度、秘めた言葉を口にしてしまったが最後、理性は本能に黒く塗りつぶされてしまう。
「もっと吸って、吸って、お願いっ、お願いだからぁ!」
「あははははッ、だいぶ自分に正直になってきたね、せんせ♪ じゃあせんせが素直なうちに、もう一回さっきの質問するね?」
ミラは教師の無様な姿を嘲笑しつつ、魔力の篭った真紅の瞳で、彼を強く凝視する。
「せんせは……ミラのこと、すき? 恋人になりたい?」
「っ……ああ、好きだ、ミラのことが、好きだ。恋人にもなりたい、いっぱいセックスしたいと前から思ってたよ、ぅぅ、どうして、俺はこんなことを……」
桂樹とミラは教師と生徒の関係だった。だが、ミラの瞳の魔力に操られて、隠し事は一切できない。桂樹は心に秘めた思いのたけを、目の前の少女にぶちまけてしまう。
「ふふ。よーく言えました。せんせ、ミラのことちゃんと名前で呼んでくれたね、黒十字なんて、名字で呼ぶ他人行儀はこれからなしだよ♪」
ミラは気持ちの昂ぶりのあまり、真紅の瞳をかすかに潤ませる。彼女の熱い秘めた気持ちを見た思いがして、強制的に操られているにも関わらず、目の前の教え子のことをこの上なく愛らしく思えてしまう。
「ミラもすきだよ。だいすき。この世で一番、何よりも、せんせのことを愛してるよ♪」
少し手足を緊張させつつ、ミラは思いのたけを口にする。
それから少し安心したように、満足そうな笑みを浮かべるミラ。そのままブラウスを脱ぎさり、黒いブラに包まれた両の胸乳を露わにする。
「もうミラは、こんなに大人なんだから」
高く張った乳房はミラの身体の動きにあわせて、ふるふると艶めかしく震え、男を興奮させるに充分すぎた。彼女は身体の自由の利かない桂樹をそのまま押し倒してしまう。
「何するんだ……やめろ、やめるんだ……」
「当然、恋人同士になったんだから??ミラとえっち、しよ」
桂樹の腰の上に跨ったミラは舌なめずりをすると、反りかえらんばかりに勃起した剛棒を取りだす。
「あは。せんせのおちんちん、すっごいおっきくなってる。カウパーでどろどろだし、ミラに血ぃ吸われてコーフンしたんだよね? くす、いけないんだぁ♪」
ミラは桂樹に見せつけるように、ショーツをずらすと、陰唇を露出させる。既に蜜を溢れさせた秘裂を大きく膨らんだ亀頭にいやらしく擦りつけてきた。
「ぁぁッ……こら、ミラ、やめろ、やめるんだ……」
愛液のぬかるみが雁首を温かく包みこみ、耐えがたい悦楽を間断なく送りこんでくる。桂樹自身も教え子のおまんことわかっていながらも先端を擦りつけ、その蕩けるような愉悦を享受してしまう。
「放課後の教室で、教え子とえっちだなんて……他の人にバレたらどうなるのかな? でもしょうがないよね。今のせんせはそんなことよりもミラとえっちしたいんだもんね?」
桂樹は答える代わりにミラの腰を掴んで、自らのほうに引き寄せる。
「あは、せんせ、積極的♪ 本当に射精したくってたまらないって感じなんだ。いいよ、ミラの処女おまんこでいっぱい感じさせてあげる」
ミラは剛直の上に、ゆっくりと腰を下ろしていく。
愛液でとろとろにふやけきった膣口が雁首にキスし、そのままずりゅ、ずりゅ、ずりゅるるるるる、と桂樹のブツを飲みこんでいく。
「ほらせんせ、よーく見て? ミラのおまんこが、せんせの早漏おちんちんを食べちゃうところ??ぁああぁぁ、んっ、はあっ♪ はぁああぁぁっ♪ ほら、せんせ、ミラのおまんこに、入っていってるよ。雁首がミラのひだひだをおしひろげて、この充実感ッ、すごすぎッ♪」
興奮に頬を紅く染めながら、ミラは桂樹を見下ろす。
処女を捧げる女の子の瞳ではなく、彼を支配する女主人の嗜虐的な目だ。
「ミラ、ずっと夢見てたの。せんせと処女セックスする日を。ミラの処女と引き換えに、せんせは一生、ミラのものッ。だってヴァンパイアとセックスするってそういうことなんだよ、んん、んんん、んんんッ!」
「ぁううぅぅッ」
ミラは一気に腰を落とし自らの処女と引き換えに、桂樹のブツを姫孔に収めてしまう。彼女の表情に破瓜した乙女の戸惑いはなく、意中の教師を逆レイプできた満足だけがあった。
「ふあっ、あぁ♪ あは、奪っちゃったね、ミラの処女。ほら見える? 真っ赤な血ぃ、ミラのおまんこから漏れだして、きてるっ……」
「ぁ、ミラ……」
ミラの言葉どおり破瓜血が、ペニスを咥えこんだクレヴァスから流れだしていた。それは桂樹がミラを支配した証というよりは、ミラに支配されたことの証だった。
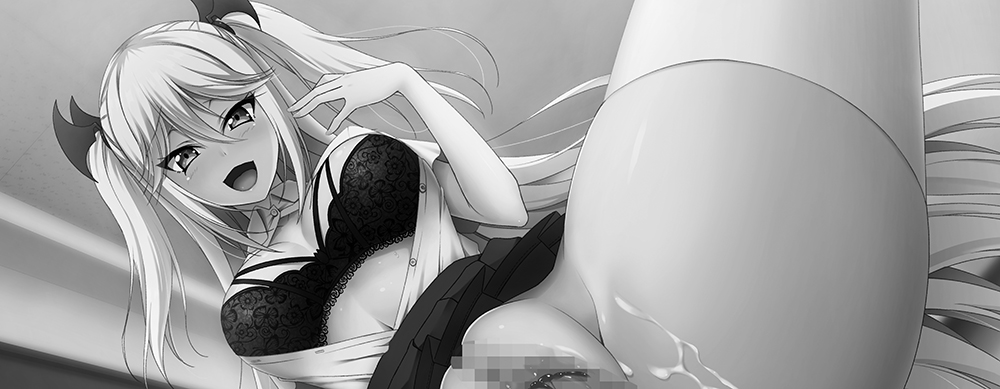
「せんせのおちんちん、ひくひくしてるのわかるよ。これで、せんせはミラのもの♪」
「え?」
ミラは処女だったにも関わらず、ゆっくりと腰を動かす。
甘い喘ぎが漏れ、痛みよりも快楽がすでに上回っているようだった。
「ヴァンパイアの一族ではね、女の子のほうが立場が上なの。男は女に絶対服従」
彼女の陶酔した顔を見ながら、桂樹はもう後戻りできないところまで来てしまったことを理解した。
教え子に血を吸われ、そして引き換えに処女を与えられたのだ。
それは平等な男女の関係ではなく、上下の男女関係。女主人と奴隷の関係だ。
「でも、いいでしょ。せんせにはミラが、最高の快楽を与えてあげる。感じすぎちゃって、どれだけ射精してもしたりないぐらいの、最高のヴァンパイアとのセックスの快楽。ほら、今もミラのおまんこがうねって、せんせのおちんちんに絡みつく感触、わかるでしょ」
言われなくとも、ミラの膣が艶めかしく蠢き、桂樹はペニスを持っていかれそうなほどの喜悦を下腹部に送りこまれつづけていた。
「ミラのあまーい汗の匂い。首筋から広がる、じわーっとした気持ちよさ。カイカンに溺れちゃお? ミラとのえっちに夢中になっちゃお♪」
ヴァンパイア少女の言葉が甘く耳朶を打ち、耳孔を犯していく。理性は蕩けさせられ、桂樹はただ快楽を貪るオスに変えられつつあった。
この続きは、9月11日発売のぷちぱら文庫『彼女が異種族だった場合。~教え子ヴァンパイアの甘トロ隷属調教~』でお楽しみください!!
(C)YUU ASUNA/Casket
桂樹はいつもどおり、教室でミラの相手をしていた。
太陽の光の苦手なヴァンパイアは明るい時間に出歩くことを嫌う。それはミラも同じで、彼女は日が暮れるまで教室で過ごしてから、家に帰ることが日課になっていた。
転校生で、まだ友達もいないミラ。その相手を桂樹がいつもしてやっていた。
ミラの手にはRHマイナスの血液ジュースのパックが握られていた。桂樹が打ち合わせで遅くなったお詫びにと、買ってきたものだ。
「悪かったって、言ってるだろ。そんなに拗ねるなよ、黒十字」
「拗ねてないし……今日はせんせが来てくれないのかな、って、ちょっと寂しくなっただけだもん」
ミラの瞳はかすかに潤み、切なそうな思いがそこから直に伝わってくる。
「せんせのことなんて、知らないッ」
ミラはぷい、とそっぽを向くと、血液ジュースをちゅうちゅうと啜り飲む。
彼女が血液を飲むたびに、さらけだされた真っ白な喉が艶めかしく動く。
美味しそうに血液ジュースを飲む黒十字ミラはまごうことなきヴァンパイアだ。
近年のヴァンパイアは人との混血も進んで、人間同様の食事でも栄養を得られるそうだが、元来は人間の血液のみを栄養にして生きる種族だ。
ミラの一族は純潔を守り通している古くからの名家で、彼女自身も人間の血液がなくては生きていけない。コンビニで血液ジュースが簡単に手に入る時代になったとはいえ、なかなか難儀な身体だと思う。
人間とヴァンパイアの共存にあたって、法律で原則、吸血行為を禁止している。もちろんミラも実際に人の生き血を吸ったことはないらしい。
桂樹がミラの放課後の時間つぶしにつきあいはじめて一ヶ月。
初めは転校生を気遣って、放課後を一緒に過ごしていた桂樹だったが、彼女の端正な美貌と年相応の愛らしい雰囲気に、次第に惹かれていった。
そうして、今、桂樹は彼女のことが本気で好きになっていた。
だが、教師と生徒。その立場を越えて、道ならぬ恋に踏みこむほど子供ではいられなくなっていた。
ふと気づくと、ミラがじっと桂樹のほうを見つめていた。
かすかに潤んだブルーの瞳に、赤らんだ頬。眼差しのあまりの熱っぽさに、そのまま引きこまれてしまいそうなほどだ。
「どうした、黒十字? 顔に何かついてるか?」
「ううん、なーんにも。ミラもせんせとお話できてうれしいなって、えへへっ♪」
「……そうか。そりゃよかった」
満面の笑みを浮かべるミラを見つめていると、本気になったまま戻れなくなってしまいそうで、慌てて視線を逸らす。
(俺が同じ学生の身分なら、失恋覚悟で告白することもできたのにな。さすがに今は、世間体ってものがあるしなあ……)
いつの間にか日はすっかり暮れ、夜の帳が降りつつあった。
ミラは桂樹の顔から視線を外さないまま、
「ねえ、せんせ?」
唐突に口を開く。
「結婚しないの?」
「け、結婚?」
いきなりミラに問われて、戸惑ってしまう桂樹。
「うん。せんせが考える理想のケッコン生活って、どんななのかなーって」
「結婚なあ。確かに親からはうるさく言われてるけど??」
結婚と問われて、ウェディングドレス姿のミラが急にイメージされて、桂樹は少し焦ってしまう。その妄想を打ち払おうとして、続いて出てきたのは裸エプロンのミラ。大きく盛りあがった爆乳のミラにエプロンはよく似合っていた。
「まあ、普通だよ。普通に専業主婦してもらって、俺が働いてかなあ。共働きだと、気持ちがラクかもだけど、ずっと家にいてほしいって気持ちも強いな」
「それ全然ロマンチックじゃなーい。愛し合ってるんなら、ずっと一緒にいるもんなんじゃないの。仕事のことばっかり……」
高校生のミラにはさすがに現実的すぎたのかもしれない。
「生きていくには仕事をしなきゃいけないんだから。それが社会のルールだしなあ」
「ルールかぁ……。じゃあ、次はミラがお話しする番ね」
いきなり桂樹の顔に自分の顔を近づけてくるミラ。吐息がかかるほどの距離で、彼女の瑞々しい唇に目を奪われてしまう。
「ミラの理想のケッコン生活は、せんせと暮らすこと」
「え!?」
いきなりそう言われて桂樹はドキリとしてしまう。
「ミラね、せんせのことが好きなの」
顔同士が触れるか触れないかの距離で、ヴァンパイアの少女は甘く囁きつづける。
「せんせの気持ち、ミラは知ってたよ。気づいちゃったの。だからミラは、せんせのほうから告白してくれるものだと思ってた。でもせんせは絶対にそうしない、いやできない……」
「ちょ、何を?」
ミラは両の眼で、戸惑う桂樹を見詰めつづける。
桂樹は本心を悟られまいと目を逸らそうとしたが、できなかった。彼女の魔力をこめられたような視線から目を離すことができない。
「ミラが聞きたいのはせんせの気持ち。せんせは……ミラのことをどう思ってるの?」
彼女に好意を持ってもらえるのは飛び上がりそうなほどうれしかったが、桂樹は教師でミラは生徒、その気持ちを受け入れることができないのも事実だ。
桂樹は嘘をつく罪悪感に押しつぶされそうになりながらも、なんとか口を開く。
「ごめんな黒十字。俺はお前とは……」
「つきあえない。だけどミラのことはすき、立場的にそれを言えない、ってこと?」
「なっ!?」
桂樹の本音を見抜いたかのように、ミラは強く指摘する。
「そんな大人の事情を聞きたいんじゃない。せんせの本当を聞きたいの」
ミラは桂樹の股の間に太腿を入れ、身体を密着させてくる。大振りの乳塊がぎゅっと押しつけられ、極上の弾力に何も考えられなくなってしまう。
「あっ……やめてくれ、ミラ……」
「せんせの心臓、すっごくドキドキしてる。ミラに告白されたから? それともミラに抱きつかれてるから?」
ぐいぐいと巨乳を押しつけられながら、ミラの甘い言葉が耳孔に流しこまれていく。
「せんせ、焦っちゃって……かーわいー♪」
「く、黒十字ッ! 先生をからかうのも大概にしろ!」
立場上、怒って見せながらも、可愛いと嘲られて、性的な悦びを感じてしまう。
「ミラはせんせの本心を聞きたいな? ねえ、教えてよせんせ??」
教え子のしなやかな手指が頬を撫で、そのまま首筋へと下りていく。背すじを走るぞくぞくとした後ろ暗い悦びに飲まれそうになってしまう。
「俺はお前とは、黒十字ミラとはつきあえな??いや、つきあわないっ! それが本心だ、他には何もないからな!」
桂樹は最後に残った理性を振り絞って、ミラを強引に引き剥がした。
「ううっ……」
ミラは怯えたように、少し後ろに下がる。彼女の前で本気で怒ったのは初めてだ。
「せんせ……ごめん、なさい」
「……いや、俺のほうこそすまない。つい感情的になってしまった」
俯きかげんに謝るミラを見て、桂樹は心が痛む。
(……いや、これで良いんだ。ミラにとっても、そして俺にとっても)
桂樹は無理やり自分を納得させる。
「……わかった。ミラ、せんせのこと諦める。やっぱり駄目だよね、せんせと恋人になるだなんて」
急にしおらしくなるミラ。どうやら彼女もわかってくれたらしい。
「今は、な。だけどもし、黒十字が大人になって、そのときにまだ俺のことが好きなら……もう一度。その言葉を聞かせてくれ」
「せんせ……くすっ、キザな台詞」
「もう、この話はこれで終わりな」
桂樹はその場が収まったことに、ホッと胸を撫で下ろす。
「じゃあせんせ、最後にひとつだけ……お願いしてもいい?」
「お願い?」
ミラは瞳をかすかに潤ませながら、じっと桂樹のほうを見てくる。
「せんせの顔……もう一度近くで見たいの。だめ?」
イヤと言える雰囲気ではなかった。
「う……わ、わかった。見るだけだからな」
「くすっ。ありがと、せんせ♪」
ゆっくりと顔を近づけてくるミラ。桂樹も内心ではミラのことを完全にふっ切ったわけではなかったから、キスの距離まで迫ってくるミラを直視することができなかった。
(これで最後か……)
桂樹は目を瞑って、ミラの甘い香りや吐息を感じる。今後はミラの身体には触れないし、触れさせない。恋人のように寄りそうのも最後だ。
「……ねえ、知ってるせんせ?」
甘くて、それでいて奈落の底に引きずりこまれ、そのまま戻ってこれなくなりそうなほど淫靡な声でミラが囁きかける。
学生とは思えないほどのエロティックな囁きに桂樹は息を飲んでしまう。
「ヴァンパイアに血を吸われた人間はね、ヴァンパイアの言うことには逆らえなくなるの。はふ、ふぅ~ッ」
「え……」
首筋にミラの湿った吐息がまとわりついたかと思うと、唇が触れる。
見るだけじゃなかったのか??そう、言い返そうとした刹那、首に突きさすような痛みが走る。
「かぷっ……んんっ」
「が、あ……!?」

直後、背すじを貫く快楽の奔流に、桂樹は声を上げることしかできなかった。
何をされたか、理解さえ追いつかない。
「な、なんだ、これっ……うううぅぅッ……ぅぅ……」
射精の快美感を何回も重ね合わせたかのような、濃密で激しい喜悦が全身を包みこんでいく。桂樹は立っていることさえできず、がっくりと片膝をついてしまう。
「はぁっ、これがせんせの血??初めて吸う、生の血? んく、んく、んくくッ、はぁああぁぁぁッ、こんなに美味しいだなんて、ミラ、吸血するだけでイっちゃいそう……せんせの熱い血を吸っちゃったら、もう血液ジュースなんて絶対、飲めない???」
「あくぅッ……黒、十字。まさか……」
桂樹はぼんやりとした頭で、ミラを見る。彼女の唇は赤のルージュを引いたかのように真っ赤な血液に彩られていた。
ミラの唇を見て初めて、桂樹は吸血されたことを理解する。
「せんせ、今どんな感じ? 頭ボーッとする? 身体が熱い?」
ミラはおずおずと桂樹の様子を窺う。
「今、何したんだ、お前……」
桂樹はミラのことを批難がましい目で見てしまう。
吸血は、法で禁じられた行為??犯罪だ。
目の前で一線を越えてしまった生徒に対して、憤るなというほうが無理だ。
「だってせんせは、全然自分に素直になってくれないんだもん。ミラ、どうしてもせんせと恋人になりたい。だから無理矢理、せんせを吸血して、素直になってもらおうと思ったの。大人の決めたルールとか関係ないもん……」
ミラの目は本気だった。
愛らしい生徒のそれではなく、美しい捕食者の目。幾星霜、人の血を吸いつづけてきたヴァンパイアの目だ。
「……もう少しせんせの血ぃ、飲んでみたいな。ね、良いでしょ?」
「い、いい加減にしろ黒十字、これ以上は……!」
ふいにミラの瞳が紅く染まっていることに気づく。
普段の碧眼ではなく、真っ赤な血で染めあげた真紅の双眸が桂樹を射抜く。
「こっち来て。ミラに血ぃ、飲ませて?」
桂樹の身体に自由意志はなかった。
(あ、あれ? どうして俺は、自分からミラに近づいているんだ?)
ミラから離れるべきだという自らの意思とは裏腹に、桂樹はミラの足元にひざまずいて、首筋を彼女のほうに晒していた。
「くすっ、優しいねせんせは。それじゃあ、いただきまーす♪」
ミラに吸血される快楽にもう一度襲われてしまえば、世間体も何もかも、投げ捨ててしまいそうで恐ろしかった。
(やめてくれ、またあの快感が襲ってきたら……!)
桂樹はなんとか抗おうとするものの、身体の自由が利くことはなく、ミラの二本の牙に再び吸血される。
首筋にめりこんでくる、ミラの鋭い歯の感触。
ずぷ、ずぷぷと。体内にミラが潜りこんでくるのがはっきりとわかる。唇のぬめりと、熱い吐息が刺さった牙の周りを覆いつくし、ヴァンパイアの少女に捕食されたことがはっきりと理解された。
「ぁ……ぁぁ……」
恐怖と緊張で、声を出すこともできない。教え子だった少女が別の何かに変質しているのをはっきりと見せつけられてしまう。
ほどなく血液が体外へと吸いあげられ、同時に蕩けるような愉悦が脳を甘く締めつけてくる。
「かぷ、んっ……ちゅぅ、んちゅっ、んっ。れろ、ちゅう」
「あひっ、血が吸われて……ぁああぁぁ……」
血が勢いよく抜けると共に、凄まじい量の快感がそれに置き換えられていった。
ペニスは一瞬で最大限勃起し、血のひと吸いごとにびくびくと先走り液を吐きだし、下着はぐっしょりと濡れていた。
「れる、ちゅ、んっ……はぁっ、最高、もっと吸うね♪ せんせ、ミラにちゅーちゅーされるの、気持ちいい?」
「や、やめて、くれえ……あひ、ぁひぃいいぃ……あぐ、あぐぐぅ……」
イキたい、精液を出したい、というどす黒い欲望が桂樹の頭を埋め尽くし、他の理性的な思考を掻き消してしまう。
ヴァンパイアの『力』のせいで手足を動かすこともままならない。桂樹はブツへの刺激を求めて腰を上下に動かす。ズボンの裏側が勃起の先にわずかに擦れるだけで、苦しみは増す。生徒の前だというのに、その浅ましい行為をやめることができない。
「やめてくれ? 違うでしょ、せんせ。心の奥底ではそんなこと考えてないよね?」
ミラは真紅に染まった瞳で、桂樹をじっと見る。
「せんせはぁ、ミラにどうされたいの?」
その紅い目に捉えられると、桂樹は桂樹でなくなってしまう。
自らの意思に反し、口が動く。
心の奥底にしまっておくべき、どろどろした薄汚い欲望が喉奥からせりあがってくる。
「俺はもっと、吸われたい……血も、精液もっ……全部、黒十字に、可愛いミラに、吸われたいッ……」
一度、秘めた言葉を口にしてしまったが最後、理性は本能に黒く塗りつぶされてしまう。
「もっと吸って、吸って、お願いっ、お願いだからぁ!」
「あははははッ、だいぶ自分に正直になってきたね、せんせ♪ じゃあせんせが素直なうちに、もう一回さっきの質問するね?」
ミラは教師の無様な姿を嘲笑しつつ、魔力の篭った真紅の瞳で、彼を強く凝視する。
「せんせは……ミラのこと、すき? 恋人になりたい?」
「っ……ああ、好きだ、ミラのことが、好きだ。恋人にもなりたい、いっぱいセックスしたいと前から思ってたよ、ぅぅ、どうして、俺はこんなことを……」
桂樹とミラは教師と生徒の関係だった。だが、ミラの瞳の魔力に操られて、隠し事は一切できない。桂樹は心に秘めた思いのたけを、目の前の少女にぶちまけてしまう。
「ふふ。よーく言えました。せんせ、ミラのことちゃんと名前で呼んでくれたね、黒十字なんて、名字で呼ぶ他人行儀はこれからなしだよ♪」
ミラは気持ちの昂ぶりのあまり、真紅の瞳をかすかに潤ませる。彼女の熱い秘めた気持ちを見た思いがして、強制的に操られているにも関わらず、目の前の教え子のことをこの上なく愛らしく思えてしまう。
「ミラもすきだよ。だいすき。この世で一番、何よりも、せんせのことを愛してるよ♪」
少し手足を緊張させつつ、ミラは思いのたけを口にする。
それから少し安心したように、満足そうな笑みを浮かべるミラ。そのままブラウスを脱ぎさり、黒いブラに包まれた両の胸乳を露わにする。
「もうミラは、こんなに大人なんだから」
高く張った乳房はミラの身体の動きにあわせて、ふるふると艶めかしく震え、男を興奮させるに充分すぎた。彼女は身体の自由の利かない桂樹をそのまま押し倒してしまう。
「何するんだ……やめろ、やめるんだ……」
「当然、恋人同士になったんだから??ミラとえっち、しよ」
桂樹の腰の上に跨ったミラは舌なめずりをすると、反りかえらんばかりに勃起した剛棒を取りだす。
「あは。せんせのおちんちん、すっごいおっきくなってる。カウパーでどろどろだし、ミラに血ぃ吸われてコーフンしたんだよね? くす、いけないんだぁ♪」
ミラは桂樹に見せつけるように、ショーツをずらすと、陰唇を露出させる。既に蜜を溢れさせた秘裂を大きく膨らんだ亀頭にいやらしく擦りつけてきた。
「ぁぁッ……こら、ミラ、やめろ、やめるんだ……」
愛液のぬかるみが雁首を温かく包みこみ、耐えがたい悦楽を間断なく送りこんでくる。桂樹自身も教え子のおまんことわかっていながらも先端を擦りつけ、その蕩けるような愉悦を享受してしまう。
「放課後の教室で、教え子とえっちだなんて……他の人にバレたらどうなるのかな? でもしょうがないよね。今のせんせはそんなことよりもミラとえっちしたいんだもんね?」
桂樹は答える代わりにミラの腰を掴んで、自らのほうに引き寄せる。
「あは、せんせ、積極的♪ 本当に射精したくってたまらないって感じなんだ。いいよ、ミラの処女おまんこでいっぱい感じさせてあげる」
ミラは剛直の上に、ゆっくりと腰を下ろしていく。
愛液でとろとろにふやけきった膣口が雁首にキスし、そのままずりゅ、ずりゅ、ずりゅるるるるる、と桂樹のブツを飲みこんでいく。
「ほらせんせ、よーく見て? ミラのおまんこが、せんせの早漏おちんちんを食べちゃうところ??ぁああぁぁ、んっ、はあっ♪ はぁああぁぁっ♪ ほら、せんせ、ミラのおまんこに、入っていってるよ。雁首がミラのひだひだをおしひろげて、この充実感ッ、すごすぎッ♪」
興奮に頬を紅く染めながら、ミラは桂樹を見下ろす。
処女を捧げる女の子の瞳ではなく、彼を支配する女主人の嗜虐的な目だ。
「ミラ、ずっと夢見てたの。せんせと処女セックスする日を。ミラの処女と引き換えに、せんせは一生、ミラのものッ。だってヴァンパイアとセックスするってそういうことなんだよ、んん、んんん、んんんッ!」
「ぁううぅぅッ」
ミラは一気に腰を落とし自らの処女と引き換えに、桂樹のブツを姫孔に収めてしまう。彼女の表情に破瓜した乙女の戸惑いはなく、意中の教師を逆レイプできた満足だけがあった。
「ふあっ、あぁ♪ あは、奪っちゃったね、ミラの処女。ほら見える? 真っ赤な血ぃ、ミラのおまんこから漏れだして、きてるっ……」
「ぁ、ミラ……」
ミラの言葉どおり破瓜血が、ペニスを咥えこんだクレヴァスから流れだしていた。それは桂樹がミラを支配した証というよりは、ミラに支配されたことの証だった。
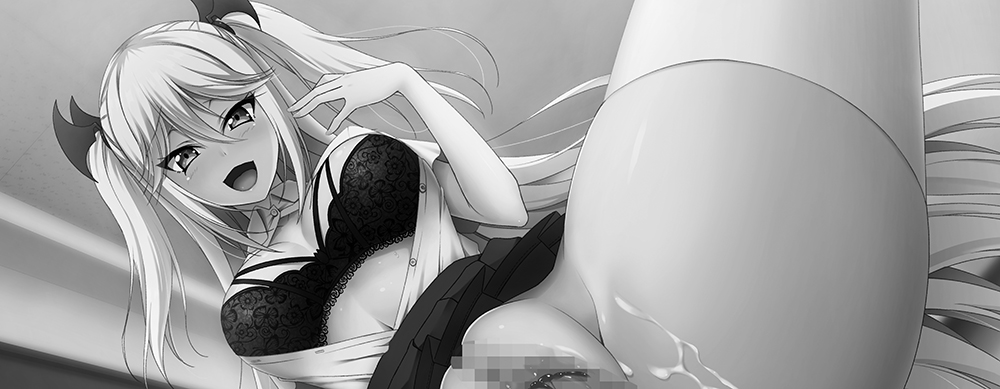
「せんせのおちんちん、ひくひくしてるのわかるよ。これで、せんせはミラのもの♪」
「え?」
ミラは処女だったにも関わらず、ゆっくりと腰を動かす。
甘い喘ぎが漏れ、痛みよりも快楽がすでに上回っているようだった。
「ヴァンパイアの一族ではね、女の子のほうが立場が上なの。男は女に絶対服従」
彼女の陶酔した顔を見ながら、桂樹はもう後戻りできないところまで来てしまったことを理解した。
教え子に血を吸われ、そして引き換えに処女を与えられたのだ。
それは平等な男女の関係ではなく、上下の男女関係。女主人と奴隷の関係だ。
「でも、いいでしょ。せんせにはミラが、最高の快楽を与えてあげる。感じすぎちゃって、どれだけ射精してもしたりないぐらいの、最高のヴァンパイアとのセックスの快楽。ほら、今もミラのおまんこがうねって、せんせのおちんちんに絡みつく感触、わかるでしょ」
言われなくとも、ミラの膣が艶めかしく蠢き、桂樹はペニスを持っていかれそうなほどの喜悦を下腹部に送りこまれつづけていた。
「ミラのあまーい汗の匂い。首筋から広がる、じわーっとした気持ちよさ。カイカンに溺れちゃお? ミラとのえっちに夢中になっちゃお♪」
ヴァンパイア少女の言葉が甘く耳朶を打ち、耳孔を犯していく。理性は蕩けさせられ、桂樹はただ快楽を貪るオスに変えられつつあった。
この続きは、9月11日発売のぷちぱら文庫『彼女が異種族だった場合。~教え子ヴァンパイアの甘トロ隷属調教~』でお楽しみください!!
(C)YUU ASUNA/Casket





